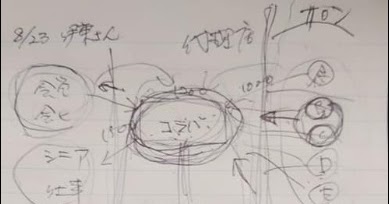≪01≫ 労働災害保険協会。これがカフカが一九二四年に四一歳直前で死ぬ二年前まで勤めていた職場だ。フェリーツェ・バウアー。これがカフカが二度婚約しながら二度にわたって婚約を解消した相手の女性の名前だ。オーストリア゠ハンガリー二重帝国。これがカフカが生まれたプラハを支配していた帝国の名だ。そこでは多数のチェコ人やマジャル人を少数のドイツ人が支配し、カフカがその血をうけついでいたユダヤ人はその二重構造から截然とはずされていた。
≪02≫ カフカはその二重帝国のシンボルのひとつであるプラハ大学で、最初のうちは化学とドイツ語を学びながら、高校時代から好きだったスピノザ、ダーウィン、ヘッケル、ニーチェを読みすすめ、すぐに親友となったマックス・ブロートと知りあってからはショーペンハウエル、トーマス・マン、ホフマンスタールを読み耽った。一番好きなのがフローベールだったらしい。
≪03≫ 父親からの注文で法律学を専攻したが、法律学を生かせず一九〇八年にふらふらと労働災害保険協会に入った。半官半民の中途半端な組織だったけれど、有能な職員として勤めた。恋をしたかったが、相手が見つからない。
≪04≫ そこでもてあました時間に文学作品をこつこつと書きはじめ、『アメリカ』や『変身』(ともに角川文庫)を仕上げた。目がさめてみたら巨大な毒虫になっていたグレゴール・ザムザの登場だ。
≪05≫ 第一次世界大戦が始まると、その渦中で、ヨーゼフ・Kの身におこった不条理をとりあげた『審判』(角川文庫)や『流刑地にて』(「カフカ・セレクションⅡ」ちくま文庫)を書いた。そのころもカフカはまだ女性に恵まれないのだが、そのうちやっと一人の婦人にめぐりあう。ミレナ・イェシェンスカ・ポラク夫人だ。この婦人はカフカの作品のチェコ語への翻訳をひきうけた女性であって、ストイックで事務的な二人の文通からはじまった関係だった。およそ実感がない関係だ。
≪06≫ この、カフカ研究者たちがいうところの、いわゆるミレナ時代に書き継いだのが問題の『城』である。けれども『アメリカ』『審判』同様に、なぜかこの作品も未完のままだった。
≪07≫ カフカは筋書きのある物語が書けないのだろうか。物語になることを拒絶しているのだろうか。それとも「不在」や「転身」を書きたくて、読み手の理解から逸れようとしているのか。どちらとも言えない。
≪08≫ 筋書きがないわけではない。たとえば『アメリカ』だ。カール・ロスマンを主人公にしたもので、『失踪者』という表題が想定されていたのだが、未完のままだったので友人のマックス・ブロートが『アメリカ』と名付けた。年上の召使いに子を身ごもらせてしまったので、両親からアメリカに放たれ、なんとも説明のつかない日々をおくるドイツ青年の話だ。
≪09≫ プロットはまるで行きあたりばったりで、冒頭からしておかしい。ニューヨーク港に着いて下船したロスマンが傘を忘れたのに気づいて汽船に戻ったところ、急に一人の火夫から「ひどい働き方」をさせられていると告白され、義憤にかられて上司に抗議してあげるのだが、埒があかない。そこに一人の紳士があらわれてその場を収めた。それが伯父のエドワード・ヤーコブという上院議員だった。その伯父に引き取られて裕福な家で英語や乗馬をトレーニングさせられた……という、この出だしからしてどうにも落ち着かない。
≪010≫ そのあとも、伯父の知りあいの銀行家らといろいろ会わされるのだが、何ら実りがない。銀行家の家に招かれ、娘のクララの歓待をうけるものの、部屋に通されると喧嘩になってしまう。クララはレスリングの心得があるらしく、組み伏せられる。まるでつげ義春だ。
≪011≫ それでもクララのためにピアノを弾いていると、手紙の入った封筒を渡され、「夜十二時にロスマンに渡すこと」という伯父の指示が書いてある。かくて青年はトランクと傘をもって着の身着のまま、またしても夜の街に放たれるのである。
≪012≫ 不安な展開だ。ロスマンは安宿を見つけ、相部屋だがそこに泊まることにした。アイルランド人のロビンソンとフランス人のドラマルシュがいた。朝になって三人で仕事を見つけようと西の方へ行き、農場の手伝いか砂金洗いでもしようということになったというのだから、とうてい物語の行方は定まらない。カフカは何も思いつけないのかよという気になる。
≪013≫ 案の定、三人は野宿をすることにして、食料と酒だけは近くのホテル・オクシデンタルで調達することになり、ロスマンが出かけるのだが、従業員の女に「泊まっていきなさいよ」と誘われる。これで三人は決裂である。ロスマンはホテルに入り、エレベーターボーイになり、タイピストのテレーゼとも仲良くなった。そんな一ヵ月半ほどがたつと、隣りのエレベーターの担当が欠員し、忙殺される。そこへ酔いがまわったロビンソンがやってきて金をせびる。そのうちすったもんだになってきて、ロスマンはホテルをクビになる。
≪014≫ こんな話が次から次に続く。乱痴気騒ぎがあれば、何百人もの白い天使の恰好の女たちがトランペットを吹いている競馬場にも行く。いったい何がアメリカか、主人公に何がおこっているのかは、なかなかわからない。ひたすら縋り、ひたすら転じていくばかりなのである。
≪014≫ こんな話が次から次に続く。乱痴気騒ぎがあれば、何百人もの白い天使の恰好の女たちがトランペットを吹いている競馬場にも行く。いったい何がアメリカか、主人公に何がおこっているのかは、なかなかわからない。ひたすら縋り、ひたすら転じていくばかりなのである。
≪015≫ というわけで、カフカは筋書きを書かなかったのではないし、物語にしたくなかったのでもない。いろいろ書いたのだ。ただ、書けば書くほど、すべては「転在」していってしまったのである。
≪016≫ カフカの長編を読んでいたころ、ぼくはしょっちゅう劇作家の別役実に会っていた。二人で碁を打ち、そのあと雑談をする。病気にかかるということの説明の奇妙について、人が人を待っているときにアタマのどこかで去来していることについて、事件はどこからどこまでが事件なのかということについて、「じれったい」はどこからじれったさがはじまっているのかについて、まあ、そんな他愛のない話だ。
≪017≫ ちょっと話しては大笑いし、また話す。遅くなると楠侑子夫人がおいしいものを差し入れてくれる。ぼくはそういう話題を他愛のないものであっても「存在待機命題」とよんでいた。こんな雑談では、話はたちまちカフカやベケットの話につながっていきかねない。
≪018≫ 別役実はカフカの短編、たとえば『流刑地にて』(白水社)などが気にいっていた。ぼくは短編のほうは高校時代や大学に入ってあらかた読みおえていたので、そのころは長編の『アメリカ』『審判』と読んできて、ちょうど『城』にさしかかっていた。『城』の話となると、別役実の咥え煙草が浮かんでくるのは、そういう事情だ。
≪019≫ 主人公は測量技師のKである。Kは、ある城の伯爵に測量のために招かれたはずなのだが、その霧深い村だか町だかに訪れたときから、いっこうに城のありかがわからなくなっている。城はすぐ近くにあるはずなのに、まことに遠い。ロスマンはアメリカに来てアメリカを見失っていくのだが、Kは最初から城を見失っている。
≪020≫ この、なかなか近づけない城というイメージは、読者をすぐさま神の畏怖のメタファーに連れこむだろうけれど、そのわりには「存在待機」が長すぎる。案の定、話はだらだらと「村」のそこかしこで続き、筋とは関係のなさそうなエピソードが脇見のように入ってくる。けれどもKは城に招かれていながら、城にたどりつけない。
≪021≫ ここでふつうなら、カフカが「場所」というものと「存在」というものを問うたというふうに見る。文学史はそのようにカフカの哲学を浮上させてきた。ところが実際には、カフカはその「場所」と「存在」の構造など描かなかったのだ。そこはむしろ「構造が描けない場所」であり、そこにいるKは「構造を問えない存在」なのである。
≪022≫ これはまさしくカフカが生まれた国のようであり、カフカがうけついだ血のようであり、カフカが就職した労働災害保険協会のようなのだ。
≪023≫ それにしても見当のない話である。いったいカフカはその話をどこでつくりあげたのか、その判定すらできなくなっているかのように見える。カフカは何かを見失ったのか。もしそうだとすると、かつてボルヘスが「カフカは中間部が欠落した作家だ」と言っていたことが、「王様は裸だ」という意味だったのかと思えたりもする。
≪024≫ ボルヘスがそのように言ったのは「カフカとその先駆者たち」というエッセイのなかでのことだった。運動する物体と矢とアキレウスが文学におけるカフカ的登場人物だということを指摘したうえで、カフカが中間部においておびただしい欠落をもっていることに言及していた。ボルヘスは、これではカフカの物語は必ず未完におわると宣託した。障害性が物語のプロットをつくるはずなのに、その障害性そのものが作品の本質であるとすれば、その物語はつねに未完でなければならないからだ。
≪025≫ そんなことをあれこれ合い間に考えたくなるほど、物語の中の城はあいかわらずいっこうに出現しない。そういう物語だ。Kもそのことで惑うということもなく、怒るということもない。ということは不条理が不条理に昇華しないのだ。そこはのちのカミュでもなく、ロブグリエや、マルグリット・デュラスでもなかった。
≪026≫ こうして何もおこることもなく、『城』は終わってしまう。未完だったとはいえ、呆気にとられる暇もない。それなのに文庫本でも五五〇ページ近くにのぼる。なのに城はあらわれない。はっきりいって読後には何も「よすが」が残らない。
≪027≫ それがフランツ・カフカの「つもり」だったのだろう。そう考えたとたん、そのことを“発見”した文学界と思想界は大騒ぎになった。カフカはいくつかの短編を除いて、長編をふくむすべての作品を燃やしてしまうように遺言して死んだのだが、友人のマックス・ブロートがそれを残した。それもあっての大騒ぎである。カフカ・ブームはそうしておこった。大騒ぎがおこったのは、城はあらわれず、審判はおりず、Kに何の進展もなかったからだった。
≪028≫ しかし大騒ぎをしたところで、物語は何も語らない。カフカはそのことについて何の説明もしなかった。そこには「届かないこと」「伝わらなかったこと」、そして「はじめからなかったかもしれなかったこと」だけが、残った。
≪029≫ 現代文学にとって、このことは大衝撃だった。どんな「よすが」も伝えないでいい文学があるだなんて、誰も思いつかなかったのである。カフカが『城』で何をしたかといえば、黙って「方法文学」を残したのである。最後に一言。生前に刊行された作品は短編しか知られていなかったけれど、ロベルト・ムージルやライナー・マリア・リルケがぞっこんになっていた。
≪01≫ 東京は今朝から雪が降ってはいない。麻布には何もおこっていないし、皇居前は静かで、戒厳令も出ていない。
≪02≫ けれども、今日は北一輝を思いたい。こんなことは初めてである。だいたいぼくは誰かの命日に何かを偲ぶという習慣がない。それなのに、今日は何かを感じたい。いや、2・26事件での北を思うだけではなく、この構想者の輪郭と相貌を勝手に思い浮かべ、なにがしかのことを考えたい。
≪03≫ ちょうど数日前から松本健一の『北一輝』単独全5巻述作(岩波書店)という驚くべき仕事が始まったばかりでもある。これまでも十全だった松本の北をめぐる研究と感想に何を付け加えられるわけでもないだろうけれど、やはりせめての望憶の思いを綴っておきたい。
≪04≫ いや、松本だけでなく、橋川文三や村上一郎や渡辺京二の北一輝などを読んできたのに、ぼくはこれまでノートに何も綴ってこなかった。『遊学』に収録した北一輝にも、ぼくは友人Sのことばかりを書いて、ついに北の何たるかを言及しなかった。
≪05≫ こういうことはいつまでたっても苦い悔恨が残るもので、それは和泉式部でもミラン・クンデラでも同じこと、感想をネジで留めておくべきときにはどこかへネジを買いに行っても、それをしておくべきなのだ。さいわい和泉式部(第285夜)やクンデラ(第360夜)にはネジをつくった。いや「千夜千冊」とは、そういうネジを1000本のうちの3分の2くらいはしっかり、手塩えをかけて特製する作業なのである。それを北一輝にもする必要がある。
≪06≫ いいかえればつまり、ついつい北一輝に「仁義」をきってこなかった。それだけである。しかし、それこそはしておかなければならないことなのだ。
≪07≫ ここに採り上げた『日本改造法案大綱』は、2・26事件の青年将校たちの聖典となったものである。
≪08≫ 内容は驚くべきもので、天皇の大権による戒厳令の執行によって憲法を3年にわたって停止し、議会を解散しているあいだに臨時政府を発動させようというふうになっている。その3年のあいだに、私有財産の制限、銀行・貿易・工業の国家管理への移行を実現し、さらには皇室財産を国家に下付して華族制なども廃止してしまおうという計画になっている。
≪09≫ そのほか普通選挙の実施を謳い、満15歳未満の児童の義務教育を10年延長することも提案する。その費用は国家が負担すべきだと書いた。英語を廃してエスペラント語を第二国語とすること、男たちが女性の権利を蹂躙するのは許さないこと、ようするに国民の人権を擁護すること、かなり進んだ社会保障も謳われている。
≪010≫ 憲法停止。天皇ハ全日本国民ト共ニ国家改造ノ根基ヲ定メンガ為ニ天皇大権ノ発動ニヨリテ三年間憲法ヲ停止シ南院ヲ解散シ戒厳令ヲ布ク。
≪011≫ しかし、この改造法案は2・26事件ではなんら浮上しなかった。まったく無視された。話題にすらなっていない。
≪012≫ 北は「改造」のためにはクーデターを辞さないでよいという方針を出していたから、青年将校が決起したのは当然だとしても、暗殺は指示していない。また臨時政府の樹立には、北は真崎甚三郎の名を霊告によって直観したようだが、これは軍部にも政府にもまったく受け入れられなかった。
≪013≫ 最大の問題は、天皇に革命を迫るという主旨で、青年将校はその大胆不敵なヴィジョンにこそ酔ったわけではあるが、これこそまったく逆の結果を招いた。
≪014≫ それではなぜ『法案』が神聖視され、かつ、みごとに打ち砕かれたのか。北がこの事件にみずから責任をとったとは思えない。逃げているとも思えない。
≪015≫ そもそも『法案』は大正8年(1919)の刊行で、それから昭和11年(1936)までは16年がたっている。もしそのあいだに北がクーデター(昭和維新)の計画の実施を練っていたとしたら、話は別である。北はそんなことはしなかった。一言でありていにいえば、書きっぱなしだった。
≪016≫ しかし、しかしである。この『法案』はその半分くらいが結局は、上から実施されたのである。それこそがマッカーサーによる戦後改革だったという評者たちは少なくない。
≪017≫ いったい、北一輝とは何をしたかった構想者だったのか。それとも何もしたくない口先だけの構想者だったのか。ぼくは長らく、この男の信条をはかりかねてきた。
≪018≫ 一人で佐渡へ渡ったことがある。両津港から若宮通りの八幡若宮神社に参ると、北一輝と弟を顕彰する安っぽいとも慎ましいとも見える記念碑があった。
≪019≫ 表に北兄弟のレリーフ、裏が安岡正篤の碑文。地元の有志が建てたという。それなら安岡などに一文を頼まないほうがよかった。安岡が北を引き寄せるのでは、北の歴史は広がらない。しかし、この顕彰碑は北一輝ではなくて、弟の令吉(日ヘンに令のツクリ)に引っ張られていると思われる。弟は兄の危険な思想にいっさい近寄らず、早稲田の教授から温厚な衆議院議員となり、戦後の自民党長老の一人となった。そういう弟を北一輝はずっとバカ呼ばわりをした。よくは事情は知らないが、安岡はきっとこの弟とも親しかったのである。
≪020≫ 湊町61番地には北一輝の生家があった。かつては酒造りの家構えだったろうが、すでに斎藤蒲鉾店というふうに代替わりをしている。しばらく佇んて、何かを感じようとしたが無理だった。
≪021≫ ついで勝広寺をたずねて椎崎墓地に入ると、そこに祖父北六太郎の墓があった。北の分骨がひっそり納められている。墓の前で手を合わせてみたけれど、北一輝と向かいあっている気はしなかった(ずっとのちのことになるのだが、大晦日近くの目黒不動に詣でていた時期があった。あるとき、そこに北一輝の墓があるのを知って、なんとも異和感をおぼえた。ここでは碑文を大川周明が書いていた。まだ安岡よりましである)。
≪022≫ 児童ノ権利。満十五歳未満ノ父母又ハ父ナキ児童ハ、国家ノ児童タル権利ニ於テ、一律ニ国家ノ養育及ビ教育ヲ受クベシ。国家ハ其ノ費用ヲ児童ノ保護者ニ給付ス。
≪023≫ そんなことを思いながら湊町をぽそぽそ歩いてみたが、佐渡からは北一輝の気配がほとんど消えていた。
≪024≫ 実際は北は素封家の酒家で生まれ育ち、父親の慶太郎は両津の町長にもなったのである。北は分限者の長男として、何ひとつ不自由しなかったはずなのだ。
≪025≫ 午後遅く、佐渡空港に近い両津郷土博物館に入って、ついに本物の北一輝に会った。全部で6冊ほどの『北日記』である。昭和11年2月28日までの日記と霊告が、ガラスの向こうでかすかに口をひらいた。そのときのぼくは何も言うことがなかった。
≪026≫ 北の霊告日記については、のちにその中身を知って驚いた。こんなことばかりを書くのは、どうみてもオカルト革命主義者としか思えない。出口王仁三郎ならともかくも、ここからぼくの北一輝を綴るのは不可能そうだった。
≪027≫ しかし他方、法華経に傾倒した北からオカルティズムと革命志向を抜き去るのも馬鹿げたことで、それならどこかで北の霊告システムをなんとか力ずくで組み伏せてでも、日本近現代史はここをネジで留めておくべきだったのである。
≪028≫ それをいつまでも放っておけば、たとえば石原莞爾の法華経も、近現代史の埒外に据えおかれたままになる。これについては、第378夜の『化城の昭和史』や第900夜の宮沢賢治のところに、少しく感想を綴っておいた。
≪029≫ 夕方近くドンデン山にバスで登って日本海を見渡してみた。なぜか渤海を感じたが、海には北一輝はいなかった。その夜は国民宿舎に泊まって、ハイネを読んで寝た。もう、40年ほど前のことである。
≪030≫ 佐渡と北一輝。そこから思いを動かそうとしているのだが、記録や研究からは、この「故郷の男」を彷彿とさせるものはあまりにも少ない。
≪031≫ それでも、憲兵少佐福本亀治の取調べに答えた記録には、「私は佐渡に生まれまして、少年の当時、何回となく順徳帝の御陵や日野資朝の墓や熊若丸の事蹟などに魅せられておりまして、承久の時の悲劇が非常に深く少年の頭に刻みこまれました」と述べている。
≪032≫ まるで承久の悲劇を自ら引きずって2・26にまで至ったと言わんばかりだが、なるほど分限者の長男としての日々はどうでもよくて、佐渡の史実に刻まれた悲哀とでもいうものが、少年一輝にうっすら覆いかぶさっていたということなのだろう。
≪033≫ 北にはその文章のどこを読んでも「文化」が埋めこまれていないのであるが(僅かな詩歌がのこされてはいるが)、憲兵を前にしての述懐にも、たとえば世阿弥が佐渡に流されたことなど、一言もふれずじまいになっている。とくに怪しみたいのは日蓮の佐渡について一度も語らなかったということだ。日蓮こそは後半生の北をまっすぐに貫いたのに。
≪034≫ 仮に土地の力(ゲニウス・ロキ)が北に大きな投影をしていないとしても、時代はぐりぐりと北を動かしていた。これは隠せない。
≪035≫ 明治16年に生まれたということは、10歳前後に自由民権運動の気運と、国会開設の動向を感じたということである。北は、いったい何を感じていたか。
≪036≫ 今ヤ大日本帝国ハ内憂外患並ビ到ラントスル有史未曾有ノ国難ニ臨メリ。国民ノ大多数ハ生活ノ不安ニ襲ハレテ一ニ欧州諸国破壊ノ跡ヲ学バントシ、政権軍権財権ヲ私セル者ハ只龍袖ニ陰レテ惶々其不義ヲ維持セントス。
≪037≫ 少年一輝は眼病を患っていた。また、写真でわかるとおり、斜視でもあった。そのことについても言いたいことはあるけれど、それは控えておく。鉄斎やサルトルやテリー伊藤をつなぐものまで説明しなければいけなくなる。
≪038≫ 読書は好きだったが、海や山とは戯れてはいない。北は自分では一度だけ「自然児だった」と言っていたことがあるが、自然児どころか、自然観照からもかなり遠かった。自分の計画を科学的だとも書いていたが、フィジカル・イメージのない構想者だった。それよりも、のちに1年にわたって上野の図書館に通いつめて『国体論及び純正社会主義』を仕上げたという“伝説”がのこったように、北はあくまで「文の人」なのである。それゆえ、少年期から作文が好きだった。
≪039≫ 漢字カタカナ交じりの文体は、いかにも北にふさわしく、北もその文体を磨いた。その文章には他人を鼓舞し、日本を立ち上がらせ、世界に対峙する力が漲っている。しかし、2・26にいたるまで、一度も「武の人」になろうとはしなかった。
≪040≫ その中学時代の作文には、はやくも尊皇心もあらわれている。尊皇心はあるのだが、天皇自身のあり方については、すでに一風変わった見方をしていた。「天皇は進化するものでなければならない」というものだ。
≪041≫ 天皇の進化――。これは北ならではの思想の萌芽とついついみなしたくなるが、これについては少し説明を要する。
≪042≫ 天皇ノ原義。天皇ハ国民ノ総代表タリ、国家ノ根柱タルノ原理主義ヲ明カニス。
≪043≫ 松本健一は、北一輝の特質が個人主義者にあると見ていた。これはあたっている。
≪044≫ 北自身、マックス・シュティルナーばりの「唯一者」たらんとするという自負をもっていた。高山樗牛の文章でニーチェの「超人」を知って大いに感嘆し、また岩野抱鳴が「自分を帝王とした世界」を称揚したことに、かなり共感したりもしている。
≪045≫ そういう北が尊皇心をもって「天皇の進化」を問題にしたいというのは、このあとの北の思想形成の謎を解く大きな手がかりになる。松本の『北一輝』(現代評論社)はその後の北一輝論を大きくリードする好著であるのだが、その論旨のひとつは、「なぜ個人主義者の北が国家主義者になったのか」という点におかれていた。
≪046≫ まさに最初の謎はこのことであるだろう。北は絶対的な個人主義者であって、「超人」としての「唯一者」でありたいと希っていた。それなのに、なぜ国家主義を提案し、国家の改造を求めたのか。
≪047≫ 超人宣言とは、進化を超越する立場の表明であろうはずなのに、なぜに「天皇の進化」などが必要だったのか。三島由紀夫だってこんなことは言ってはいなかった。
≪048≫ この謎を解くには、いったんこの時代舞台に戻る必要がある。もういっぺん佐渡にまで戻ることになる。ただしそれは日蓮や世阿弥の佐渡ではなく、佐渡新聞にさかんに論評を書いた明治半ばの佐渡である。
≪049≫ 北一輝が自由民権運動に影響をうけていたことは、ほぼ資料があきらかにしている。研究も進んでいる。
≪050≫ 自由民権思想にそもそも近代の個人主義をめざめさせる動機がふんだんに動いていたことも、いまさらいうまでもない。個人主義とむすびついたから、まさに「民権」だった。
≪051≫ しかし、この自由民権的個人主義は、中江兆民がなかなかうまいことを言っているのだが、実のところは「恩賜的の民権」(三酔人経綸問答)だった。天皇という君主から与えられた恩賜の民権だ。この日本的民権は、半分は民衆から(といっても板垣退助の土佐自由党から秩父の農民までを含んでいたが)、半分は上から降りてきたようなところがあって、それが日本的に折衷した。
≪052≫ 北が佐渡にいたとき、まさにこのような“民権個人”の風潮がこの島にも巻き起こっていたわけなのだ。
≪053≫ そこで北は考えた。このように天皇と個人がどこかで連動しているとなると、個人が「超人」や「唯一者」をめざしているときは、天皇や君主にもそうなってほしい。「天皇の進化」という言葉には、こうしたニュアンスがこめられていた。
≪054≫ 日本国民一人ノ所有シ得ベキ財産限度ヲ三〇〇万円トス。私有財産限度超過額ハ凡テ無償ヲ以テ国家ニ納付セシム。
≪055≫ 19世紀後半、ロシア・ドイツ・日本などの後発で資本主義をめざした国が何をしようとしたかといえば、国家主導による富国強兵をめざした。
≪056≫ 封建遺制がいろいろのこる国情のなか、この目標を完遂するには、「ツァール」「カイゼル」「天皇」というカリスマ権力を歴史的に温存し、その絶対主義的支配力を有効に活用しなければならなかった。それが後進国の戦略というものである。しかし一方、資本主義を浸透させるということは、アダム・スミスの言うとおり、そこに個人の判断が自由に動く必要がある。国民に個人主義が浸透することが資本主義の裏シナリオなのである。明治政府が立身出世を煽り、大学が知識の自由を与えようとしたのは当然だった。
≪057≫ けれども個人主義があまりに放蕩を広げるなら、ここに民権の歪みもおこる。そこで絶対主義を背景とした近代国家では、君主自身が変質し、臣民を国民になっていくプロセスを立憲君主制のなかで共有する必要もある。
≪058≫ ここで漱石ならば、国家の危機と個人主義の発揚と自己の脳天への鉄槌を切り替えて考えることができたはずである(第583夜)。しかし北一輝は、「個人の進化」(超人化)と「天皇の進化」(国体の進化)とがひとつの社会現象になるものと見た。
≪059≫ これは北の不幸の始まりである。なぜならば、天皇に言及し、あまつさえ天皇の変質に言及して、日本の明日を語ることなど、まだこの国には許されていなかった(いまなおこのロジックをまともに提起できる者はいないままである)。
≪060≫ それなのに、北はここを突っ切った、そして23歳にして一挙に書き上げたのが『国体論及び純正社会主義』という傑作だった。
≪061≫ 早熟の23歳の著書は、明治30年台の日本を、帝国憲法からみれば社会主義国家で、藩閥政府と教育勅語でみれば天皇制専制国家で、社会経済面からみれば地主とブルジョワが支配する資本制国家であると、3段にみなしている。このうち、最初の国家観に立って、あとの二つを打倒してしまうというのが、北の革命になる。
≪062≫ この異様な見方の前提になっているのは、北が、明治の維新革命は日本を社会主義国家にする可能性を開いたと見ていたということである。そして、それは帝国憲法によって法的に確立された。北の言葉でいえば「物格」が「人格」になったのである。
≪063≫ そのように見ると、天皇専制という現状は、憲法が定める国体とは適合していないということになる。そこでこれを変更して天皇制を進化させ、さらに地主とブルジョワが占める制度をくつがえすことが、北のいう第二維新革命の骨法だった。
≪064≫ この破天荒な著書は発売5日にして発禁になった。これは北を逆上させていく最初のトリガーになる事件だが、そのぶん、幸徳秋水らの社会主義者たちからは人気を得ることともなった。河上肇も片山潜も書評を書いた。
≪065≫ けれども、いまなら多少の見当がつこうけれど、北の社会主義はマルクス主義とはまったく交差していない。北は北一輝であって、その独自の理論の組み立てに、何も社会主義者の輸入理論などを頼る必要はなかったのである。それが社会主義者の歓心を買ったために、北に変な自信をもたせた。
≪066≫ しかも北には国体の純正化こそが重要であって、それには民衆の蜂起がおこるよりも、天皇の軍隊の変質こそが必要だったのである。これは社会主義者からみればまったくおかしな議論であったはずなのに、このときは誰もそれを指摘しなかった。
≪067≫ が、この著書はそんなことをアピールする前に、東京日日新聞などから不敬の対象になるとキャンペーンされて、まさに天皇制日本からの弾圧を食らったのである。
≪068≫ 北はこの弾圧には動じなかった。それどころか、天皇制政府というものは、このようにいつも過ちを犯し、手続きを踏み誤るものだとみて、いずれ天皇制をゆさぶるのはたやすいことだと、とんでもない過信をしたようだった。
≪069≫ 生産的各省ヨリノ莫大ナル収入ハ殆ド消費的各省及ビ下掲国民ノ生活保障ノ支出ニ応ズルヲ得ベシ。従テ基本的租税以外各種ノ悪税ハ悉ク廃止スベシ。
≪070≫ その後の北が宮崎滔天らの「革命評論」に迎えられ、孫文・黄興・宋教仁らの中国革命同盟会の活動に接することになっていったのは、日本の天皇制を動かすにはまだ時間がかかるとみて、いったん中国革命にテコ入れをして、その余勢をかって日本に革命を再帰させようと考えたからである。
≪071≫ むろん『国体論及び純正社会主義』だけで、日本革命がおこるとも考えていない。北も、そういうことは察知していた。察知したがゆえに、その国家革命の意志を中国に託そうともして、明治44年10月、中国に渡ってしまった。亡命ともいうべき「支那革命への没入」をはかったのだ。『支那革命外史』の執筆がこうして生まれた。北輝次という本名を北一輝と中国ふうに改名したのも、このときである。
≪072≫ 北はここから10年以上の時間を中国に投入する。けれども、ここでふたたび北の不幸が加算する。中国では五四運動が勃興し、排日運動が北をとりまいたのである。
≪073≫ 北は「さうだ、日本に帰らう」と決意する。そして帰る以上は、支那革命の理想を日本に翻案するべきだと思われた。『日本改造法案大綱』は、中国から日本への転換あるいは回帰の正当化のために書かれたとしか思えない。
≪074≫ 2・26事件の青年将校たちが『日本改造法案大綱』をバイブルとしたことは、最初に述べた。この一書が昭和維新の聖典だった。北はこれを日本に帰る前の上海で書いた。大正8年である。
≪075≫ その前年、満川亀太郎は老壮会をおこし、そこに大川周明が加わって猶存社が結成された。その大川が上海に密航して北に接触し、『日本改造法案大綱』の原稿を持ち帰った。満川はさっそくこれを謄写版印刷に付し、47部を配布した。
≪076≫ 集約すれば、この『法案』の指示するところは「天皇の活用」と「国家社会主義の実践」という二つの構想が、奇妙に結びついたものになっている。
≪077≫ この結びつき方は高度といえば高度、思慮がないといえばいかにも慌てて書いたというもので、滝村隆一の『北一輝』(勁草書房)や渡辺京二の『北一輝』(朝日選書)がそのことを分析していたけれど、いずれにしてもこれが青年将校に理解できたとは思えない。
≪078≫ 大正12年、『法案』は改造社から刊行される。甚だ伏字の多いものだった。いま、みすず書房版の本書にもその伏字版が収録されていて、これを見ていると、ぼくは急に北一輝の宿命を痛打された思いになる。
≪079≫ 何を北に向かって言えるものか。われわれは黙って北を感じるしかないではないかという気分だ。
≪080≫ けれども、『法案』が2・26の青年将校たち、とりわけ『法案』の伏字部分にすべて書きこみをしていた西田税などに、さて、どんな果敢な負荷をもたらしたのかということを思うと、「天皇の活用」という北のヴィジョンがあまりに細部にわたりすぎて(どう考えても「天皇の活用」と「国家社会主義の実践」は別々のプランにしかなっていない)、かえってどんな青年たちにもその計画の意味を伝えられなかったのではないかという危惧をもつ。
≪081≫ 「クーデター」ハ国家権力即チ社会意志ノ直接的発動ト見ルベシ。其ノ進歩的ナル者ニ就キテ見ルモ国民ノ団集ソノ者ニ現ハル、コトアリ。日本ノ改造ニ於テハ必ズ国民ノ団集ト元首トノ合体ニヨル権力発動タラザルベカラズ。
≪082≫ 北一輝には、天皇を拝跪する気持ちがまったくなかった。北がほしかったのは、天皇に代わって自分を「超人」として拝跪してもらうことなのだ。
≪083≫ 大川周明は、そういう北の傲慢な「魔王」ぶりが気に食わず、袂を分かっていく。けれども大川のところにいた西田税は、北一輝についた。北はすでに大正15年に『法案』の版権を西田に譲っている。厳密にいうのなら、この時点で北は自分の日本革命企画を、自分の手から放してしまったのである。
≪084≫ そのかわり、北は新たに拝跪する絶対世界を得た。それが法華経の世界である。
≪085≫ ここでヴィジョンががらりと上下に切り替わる。仏が天皇の上に立ち、その仏の高みから「天皇の軍隊」に指令をくだすという、それまでの北の従来にないヴィジョンがここに起動した。2・26事件の渦中、北が仏前に祈っていたというのは、きっと本当のことだろう。
≪086≫ 一方、磯部浅一は2・26事件の直後に、こう呻吟していた。「日本には天皇陛下はおられるのか。おられないのか。私にはこの疑問がどうしても解けません」。
≪087≫ 青年将校たちにとっては、天皇を悪用する「君側の奸」を除去することがクーデターだったのである。しかしながらいくら天皇の権威に群がる「君側の奸」を打ち払っても、天皇は姿をあらわさなかった。それどころか、天皇は将校決起に激怒した。
≪088≫ 天皇は青年将校のテロリズムを憎んだだけではなかった。自分を騙る者に激怒した。
≪089≫ おまけに、天皇の怒りは青年将校の向こう側には届いていない。皇道派の青年将校たちに対して、いわゆる統制派とよばれた幕僚将校たちこそ、天皇中心の“錦旗革命”を標榜しつつ、実は天皇の“大御心”を信じてもいないくせに騙ろうとしていたはずなのである。しかし、天皇は統制派には文句をつけなかった。
≪090≫ 維新革命以来ノ日本ハ天皇ヲ政治的中心トシタル近代的民主国ナリ。何ゾ我ニ乏シキ者ナルカノ如ク彼ノでもくらしいノ直輸入ノ要アランヤ。
≪091≫ 日本には幕末維新を通して、互いに異なる二つの天皇論が並列処理されてきた。
≪092≫ ひとつは吉田松陰に代表される精神派(社禝派)で、民族民権の根拠として天皇を中心とした組み立てをしたいと希う考え方である。もうひとつは横井小楠に代表される合理派(近代派)で、天皇を制限君主として立憲君主制のもとに近代国家を組み立てたいという考え方だ。
≪093≫ この二つは、明治維新では表向きだけで合流したにすぎなかったのに、自由民権運動をへて帝国憲法にいたる過程では、天皇を精神的にも合理的にも活用するという両義的体制の確立に向かっていった。大久保利通や伊藤博文はあきらかにこのことを知って、明治立憲君主の体制を整えた。
≪094≫ そこに大きな二枚舌が動いた。大久保・伊藤は、天皇が政府・軍部のトップにとっては単なる天皇機関説のシンボルにすぎないことは常識でありながら、これを公言することは絶対にしてはならぬものと戒めていた(いわば密教的天皇論)。一方、政府や軍部の下部組織や国民に対しては、天皇が絶対服従をもたらす崇敬の対象でなければならないことは絶対公言によって伝わるべきものだと考えた(いわば顕教的天皇論)。
≪095≫ 日露戦争前後から、この絶対秘密と絶対公言という両義的な天皇活用度は一挙に広まっていく。明治政府からすれば事態は好ましく誘導されていると思われたはずである。
≪096≫ ところが、そこに立ち現れたのが北一輝だったのである。北はその鋭い洞察力をもって、密教的天皇論を“合理”として、“近代”として、見抜いてしまったのだ。
≪097≫ 皇道派の青年将校は、最初から最後まで顕教的天皇論の中にいた。青年将校のヴィジョンは、そもそもが権藤成卿(第93夜)や橘孝三郎の農本主義に近かった。
≪098≫ それなのになぜ北の構想に従えたかといえば、その構想が、密教・顕教ともに出発点を同じくしたと見えた明治維新の原点(国家社会主義の原点)を継ぐ、第二維新革命と定義されていたからだった。
≪099≫ 2・26に青年将校を駆り立てたのは、直接には相沢三郎が永田鉄山を一刀のもとにを斬り捨てたことだった。また、農村疲弊の突破にはやる熱情の噴出だった。決起が2・26に定められたのは、青年将校の本拠である第一師団が満州派兵の“用具”にされていった急転直下の事情を食い止めたかったからだった。
≪0100≫ かつてはぼくも見間違えていたのだが、宇垣一成大将を据えた昭和6年の三月事件や建川美次少将を据えた十月事件は、あれは2・26への前哨などではなくて、むしろ統制派の軍事クーデターのための布石であったのだ。
≪101≫ そうだとすれば、北一輝の改造法案構想はまさにこの統制派の布石をとっくの昔に読み切ったものだったわけで、だからこそ、統制派からすれば5・15や2・26の重要人物暗殺の連打によって、北と青年将校が共倒れになることは、願ってもないことだったのである。
≪102≫ もうひとつ、ここに動いたものがある。それが第914夜の『この国のかたち』にのべておいた統帥権干犯の問題だ。天皇を実用的に持ち出したのは、北一輝ではなくて、結局軍部幕僚たちだったのである。そして、司馬遼太郎が期待した日本の「真水」は、北によってではなく、青年将校の嚥下に飲み下されたのだった。もはや詳しい感想を述べるまでもないだろう。
≪103≫ 恋厥(れんけつ)という。恋い焦がれる心情をいう。2・26の青年将校にはあきらかに恋厥がある。
≪104≫ しかし、恋厥をもって希望をもつか、絶望も辞さないかというと、ここからは思想や構想を超えるものが出てくる。雪降りしきる2・26は、最後の最後のところで、この問題に抱かれる清浄なものを流出させた。
≪105≫ のちに三島由紀夫は『文化防衛論』に、「絶望を語ることはたやすい。しかし希望を語ることは危険である」と書いた。それもそうであろう。三島はこのとき磯部浅一一等主計の遺稿のことを言ったのだ。
≪106≫ けれども、2・26事件にはまた、安藤輝三大尉の行動というものもある。安藤はクーデターがすでに天皇から見放されたことを知ったのちも、希望も絶望ももたずに、永田町付近の一角をただ一心に見守り続けたのである。
≪107≫ いまふりかえれば、こういう北一輝がいてもよかったような気がする。事件というもの、ときにシテよりもワキによってその本来を告げるものなのだ。
≪108≫ それならそこには「文の人」も「武の人」もない舞台があってもよかったのである。佐渡がただ沛然と湧きおこる複式夢幻の革命児があってもよかったのである。
≪109≫ 只天佑六千万同胞ノ上ニ炳タリ。日本国民ハ須ラク国家存立ノ大義ト国民平等ノ人権トニ深甚ナル理解ヲ把握シ、内外思想ノ清濁ヲ判別採拾スルニ一点ノ過誤ナカルベシ。
≪01≫ 二十世紀がまもなく終わるという時期、出版界ではさまざまな「まとめ」が試みられた。世界中で総括と反省と自慢と批評による興味深い試みが連打されたが(放送業界でも記念番組が多かった)、日本では毎日新聞社の「シリーズ20世紀の記憶」が二十世紀をふりかえるということでは至極まっとうな企画であった。企画はまっとうだが、その編集構成感覚はなかなかぶっとんでいた。
≪02≫ どこかで歴史的予定調和にまとまりかねない見方を裏切りたいというような視点もまじり、痛快な出来を示した。西井一夫が指揮をとったのが、こうさせた。編集賞ものだろう。西井は以前は「カメラ毎日」でその腕を鳴らしたグラフィズムに強いエディターシップの持ち主である。「カメ毎」の前編集長だった山岸章二が突然に自殺したあとを引き受けたから、いろいろ苦労もあったはずだ。エディトリアル・デザインには鈴木一誌が腕をふるった。表紙は一冊ずつすべて意匠を変えている。だからムックっぽい。
≪03≫ ぜひとも全冊(二〇冊+別冊年表)をナマで見てもらうのがいいのだが、ディケード(十年単位)で区切っていないこと、巻構成に均等な内容配分を振り分けていないことがいまなお斬新だ。よほどおっちょこちょいか、よほど自信がなければこうはできない。
≪04≫ たとえば「1900‐1913 第2ミレニアムの終わり 人類の黄昏」「1945年 日独全体主義の崩壊 日本の空が一番青かった頃」「20世紀キッズ 子供たちの現場」「1969‐1975 連合赤軍“狼”たちの時代 なごり雪の季節」「1989年 社会主義の終焉 オタクの時代」「1990‐1999 新たな戦争 民族浄化・カルト・インターネット」というふうなのだ。やりすぎや手拍子もある。「1976‐1988 かい人21面相の時代 山口百恵の経験」には呆れた。
≪05≫ 刊行元が新聞社の毎日だということもあって写真も選りすぐってあって、どちらかといえば人物中心になっている(事件型ではない)。プロファイルっぽい。そうそう、このシリーズは一部を除いて全ページがモノクロなのだ。それなのにドキュメンタリーなテイストに巻き込まれていないのは、編集部がピックアップする視点がすこぶる文化思想的で、かつ差分的であるからだろう。鈴木のレイアウトもモノクロを感じさせないものになっている。
≪06≫ 本巻は一九二〇年代を扱っているという点では、全巻のなかでは最もオーソドックスな巻立てだ。それでもタイトルの「ロストゼネレーション」に「ユリシーズと関東大震災」というサブタイをもってくるところが、西井チームの自慢なのである。
≪07≫ 一年ずつに橋本治による「年頭言」が入ってくるのも雑誌めく。橋本の文章は一ページまるまるのもので、歴史家がその一年の世界史を案内しているという記事ではない。さすがにそのつどの現代史を切り取ってはいるが、文体はまるで個人の感想に傾くエッセイだ。これも西井の狙いだったろう。
≪08≫ 編集構成を大きく眺めると、ロストゼネレーションを代表するヘミングウェイ、フィッツジェラルド、ジョセフィン・ベーカー(パリで衝撃的なデビューを飾った黒人ダンサー)がフィーチャーされ、そこにジョイス、孫文の死、関東大震災、カポネと暗黒街、ニューヨーク摩天楼、ロトチェンコのタイポグラフィ、リンドバーグの飛行機、ラジオの登場などが交差する。読み物ふうのハイデガーには木田元の、ニジンスキーには三浦雅士の、エコール・ド・パリには深谷克典の解説が付された。
≪09≫ ワイマール文化、表現主義の実験、ジャズの熱狂、日本のメディア文化、シュルレアリスムの抬頭をもう少し採り上げてもよいのに、このあたりは不発になっている。日本のトピックでは同潤会アパートが建てられていった経緯と写真、松岡虎王麿の南天堂の周辺の出来事が特筆されているのが、めずらしい。
≪010≫ ロストゼネレーションという呼称は、第一次世界大戦に従軍体験をした若者たちが抱いた虚無感をあらわすべく、当時の天下一の突っぱり姐さんだったガートルード・スタインが言い出した時代用語である。この稀代の、レズビアンで美術コレクターでもあった女史は、「あんたたち失われているのね」と言ったのだ。
≪011≫ すぐさまヘミングウェイ、フィッツジェラルド、ドス・パソス、フォークナー、E・E・カミングス、マルコム・カウリーらがその刻印に応じた。いや、甘んじた。かれらは国外離脱者でもあって、多くが「パリのアメリカ人」としてやるせない日々をおくった。それを迎え撃ったのがジョイス、エリオット、エズラ・パウンド、モンパルナスのキキ、マン・レイ、コクトー、ココ・シャネルたちのヨーロッパ勢だった。
≪012≫ こうした連中をのちのちまでアメリカでは「失われた世代」とか「自堕落な世代」と呼び、フランスではしばしば「一九一四年世代」「炎の世代」(génération au feu)などと呼ぶ。行き場のない世代、迷える世代、それゆえ日々の享楽に耽った世代なのである。ちなみに、この世代の子供の世代がビート・ジェネレーションに、そのまた子供の世代がヒップ・ジェネレーションになる。
≪013≫ こうした連中をのちのちまでアメリカでは「失われた世代」とか「自堕落な世代」と呼び、フランスではしばしば「一九一四年世代」「炎の世代」(génération au feu)などと呼ぶ。行き場のない世代、迷える世代、それゆえ日々の享楽に耽った世代なのである。ちなみに、この世代の子供の世代がビート・ジェネレーションに、そのまた子供の世代がヒップ・ジェネレーションになる。
≪014≫ これはいったい何だろうと思い、雨宮処凛の『ロスジェネはこう生きてきた』(平凡社新書)、岩木秀夫の『ゆとり教育から個性浪費社会へ』(ちくま新書)などを読んでみたが、軌道電車がない都市でメル友に言葉を費やしながら、姿の見えない管理社会を敵にまわそうとしている叫びだけが、伝わってきた。
≪015≫ さらについでに余計なことを言っておくと、戦後日本にはロスジェネに及んだ“かたまり”が、それぞれ流行語大賞ふうの世代俗称になっている。
≪016≫ 一九四七年~四九年生まれの「団塊」の世代、五〇年代後半~六四年生まれの「新人類」、六五年~六九年生まれの「バブル世代」、七〇年~七四年生まれの「団塊ジュニア」、八七年~二〇〇四年生まれの「ゆとり世代」、その途中に七〇年代生まれを中心にした「ロスジェネ」がいるというふうになる。
≪017≫ まあ、そう言われてもまったく何の説明にもならないだろうが、残念ながら日本にはガートルード・スタインがいなかったのである。
≪018≫ 話戻って、一九二〇年代はロストゼネレーションだけの時代ではない。欧米においても日本においても失われたものを引きちぎるほどの文化の灼熱期だった。ぼくが二十世紀のディケードとして「文化の多彩な爛熟」に注目するのは、このローリング・トゥエンティーズ(Roaring Twenties)だけである。
≪019≫ 第一次世界大戦が一九一八年に終わり、アメリカ大統領ウォーレン・ハーディングが「ノーマルシー」(Normalcy=常態に復する)を選挙スローガンに掲げたのだが、戦争の終結がもたらした解放感は常態復帰などにとどまらなかった。
≪020≫ まずは技術文化が目を見張るものになった。自動車の開発(競争レースが過熱した)、鉄道の充実(旅行がはやった)、飛行機ブーム(リンドバーグの大西洋横断とツェッペリンの飛行船が世界を周遊して耳目を驚かせた)、無声映画とトーキーの氾濫(ドイツ映画の『カリガリ博士』やチャップリン、バスター・キートンらの喜劇が当たった)、カメラの技術革新(ライカが世界を瞠目させた)、ラジオの一挙的普及(アメリカの商業放送がKDKAによって一九二二年ピッツバーグで開始した)、都市における建築ラッシュ(ニューヨークの摩天楼が完成した)などが連打された。つまり目に見えるインフラがことごとく一新されたのだ。
≪021≫ そんななかで、ヨーロッパでは一九二二年にジョイスの『ユリシーズ』とエリオットの『荒地』が登場して、文学を一変させたのである(荒地とは「死の国」のこと。その詩は一人称ではなく多人称だった)。こんな大きな文芸事件はめったにないが、それだけではなかった。
≪022≫ すでに一九二〇年にトリスタン・ツァラがチューリッヒからパリに来てダダを撒きちらし、そこにフランシス・ピカビアやマン・レイやデュシャンや、ミロ、マッソン、キリコ、モディリアニ、エルンストがリプレゼンタティブに林立していった。まだ若造だったコクトー、ピカソ、サティはとっくに「バレエ・リュス」のゲイのロシア人ディアギレフの挑発でおかしくなっていた。
≪023≫ ぼくが好きなエピソードもある。ピアニストのジョージ・アンタイルがパリに来て作曲家に転じ、ジョイスを育てたシルヴィア・ビーチの書店「シェイクスピア&カンパニイ」の二階に借り住まいしたことだ。アンタイルの《野生のソナタ》はいま聴いてもぞくぞくさせられる。
≪024≫ これらの動向のなかで見落とせないのは、ドイツ表現主義が絵画においても文芸においても映像においても、歪んだ心理の変形ヴィジュアル化をもたらしたことと(前衛グループ「ブリュッケ」と「青騎士」が先頭を切った)、これが無意識に挑むフランスのシュルレアリスムの抬頭につながっていったことだろう(アンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』の起草が一九二四年だ)。その背後にはキャバレー文化とカフェ文化が波打っていた。ヨーロッパにおけるダダ、未来派、表現主義、シュルレアリスムなどの「逆上するムーブメント」については、いまこそ日本のロスジェネ以降の世代がつぶさに観察するといい。
≪025≫ この時代、アメリカでは「ハーレム・ルネッサンス」が高じて、ジャズエイジが誕生した。一九二一年にブラックスワン・レコードが開設された。当時の洗練された感覚と頹廃的な感覚はほぼすべてジャズが担ったと見ていいだろう。ハロルド・スクラッピー・ランバートの高音には誰もが胸をかきむしられた。
≪026≫ 当時のジャズはいまだ社会的少数派のものだ。大衆の多くはスウィートミュージックに走り、少数派のハードコアはホットミュージック、あるいはレイスミュージックとみなされていた。そのなかでルイ・アームストロングが意味のないスキャットを延々とインプロし(最近のヒップホップにはこれがない。つまり黒いダダがない)、シドニー・ベチェットがサックスを使えるようにした。これらを吸引して、二〇年代のおわりにはそうとうな変わり者だったデューク・エリントンのビッグバンドさえ登場した。
≪027≫ みんな体を動かしたがっていたとも言える。フォックストロット、ワルツ、タンゴ、チャールストン、リンディホップが流行し、全米にダンスホールが次々に開場して、ボブ・ダグラスが黒人ばかりのバスケットボール・クラブをつくった。コットンクラブでは着飾った紳士淑女がジャズに酔いしれた。
≪028≫ 禁酒法が施行され、そこにアル・カポネを代表とするギャングが横行したことも、アメリカのローリング・トゥエンティーズを異様に彩っている。この「異様」が次から次に対抗文化の様相を呈したのが、二〇年代ではとんでもなく看過できないことになっていった。シカゴやニューヨークやサンフランシスコにスピークイージー(潜りの酒場)が出現して、妖しい女とギャングが結びついていったことなど、いまや再現するすべがない(タランティーノやフランク・ミラーやロバート・ロドリゲスは復活したがっている)。
≪029≫ そこに醒めた目でコートの衿を立てて登場したのがレイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットのハードボイルドだ。短文が連なる文体には「女はバケツのような口をして笑った」といったあけすけな描写が切り刻まれていた。いまなおアメリカ映画はこの時代のギャングを主人公にした哀切を得意気に描き続けている。
≪030≫ ドイツでは表現主義だけでなく、ワイマール文化の浸潤とバウハウスのデザイン教育を重視するべきだ。第一次世界大戦で大敗したドイツは一九一九年に最悪の経済状態になっていた。そのなかで組み上げられていったのがワイマール共和国だ(一九一八~一九三三)。ヒトラー政権が確立するまでのドイツはもっぱらワイマール文化がその習熟した方法論によって牽引した。二〇年代のベルリンはワイマール文化の頂点だった。
≪031≫ ワイマール文化の特徴は「知の再構築」にある。マンハイム、エーリッヒ・フロム、アドルノ、ホルクハイマー、マルクーゼ、カッシーラー、フッサールらの知識人が毎夜にわたって世界の構成方法をめぐって議論した。こういうところがドイツ人の徹底した理論根性だ。かれらのすべてがシェーンベルクやアルバン・ベルクの無調音楽や十二音階技法の意味を考えていたことにも驚いたほうがいい。
≪032≫ ヴァルター・グロピウスがワイマールにバウハウス(「建築の家」という意味)を建てたのは一九一九年のことだった。すぐさま構造・構成・構匠それぞれのデザインは技法を伴っていることが告知され、ハンネス・マイヤー、クルト・シュヴィッタース、パウル・クレー、ヨハネス・イッテン、モホリ゠ナギらが次々に講師に立った。バウハウスがなかったら今日のデザインはない。
≪033≫ 時を同じくして、途方もなく画期的なメソッドを提出していったのがロシアだ。ドイツ表現主義に比肩する構成主義にはカンディンスキーからマレーヴィチまでが登場し、バウハウスに比肩するデザインではロトチェンコやリシツキーらが登場し、これらを覆ってエイゼンシュテインの驚くべき映像技法が開花した。あの「オデッサの階段」の名場面で唸らせた《戦艦ポチョムキン》は一九二五年の制作だったのである。エイゼンシュテインはメイエルホリドの演技技法を習得し、独特のモンタージュ理論を打ち立てた。日本の歌舞伎の様式にいちはやく注目し、日本人が伝統を見離して欧米の猿真似をすることに苦言を呈した。
≪034≫ その一方では、さきほどもチョイ出ししておいたディアギレフによるロシア・バレエ「バレエ・リュス」がヨーロッパをひっくりかえしていた。ニジンスキー、アンナ・パブロワ、イーダ・ルビンシュタイン、タマラ・カルサヴィーナらの夢幻のような踊りは、世界中の誰も見たことのないものだった。今ならさしずめ、冬季のフィギュアスケート、夏季のシンクロナイズド・スイミングのロシアチームに瞠目するようなものだろう。ぼくはこのロシア浪漫の原動力がどこから来るのか、ぜひ知りたい。
≪035≫ ロシア人の二〇年代については、レーニンやトロツキーの革命活動とその文章力にも注目したい。レーニンはマッハの感覚論について、トロツキーは未来派について、偏ってはいたが、鋭い考察をしてみせた。ぼくはソチの冬季オリンピックの開会式の映像演出にロトチェンコもレーニンも出てきたことに喝采をおくったものだ。
≪036≫ 日本はどうだったかというと、一九二〇年が大正九年になる。第一次世界大戦で火事場泥棒めいた景気を貰っていた日本は、その濡れ手で粟の反動でしばらく戦後不況に悩まされるのだが、しかしながら、そんな不景気と大正デモクラシーの中でこそ二〇年代文化が切り拓かれた。
≪037≫ 一九二〇年ちょうど、読売新聞が文語体から口語体にすると、二年後に「週刊朝日」(初期は旬刊)と「サンデー毎日」が、三年後に「文藝春秋」が創刊され、同じころ蒲田には撮影所が設立されて「キネマの天地」を謳歌した。サワショーこと沢田正二郎の新国劇が《国定忠次》を上演したのもこのころだった(のちまで続くチャンバラ・ブームはここからおこる)。
≪038≫ こうして開花した大正中期文化は、一九二三年の関東大震災で決定的な打撃を被った。また、それまで破竹の勢いでアナキズムを激情させていた大杉栄が震災とともに殺害され、ここに幸徳秋水以来の社会主義文化も退嬰しそうになっていくのだが、そこからがしぶとかった。
≪039≫ まずは帝都東京がめざましく復興されたのである。後藤新平が旗を振った。かくて昭和が始まる一九二六年前後からは東京のメインストリートにはモガ・モボ(モダンガール・モダンボーイ)が溢れ、カフェーの女給文化に文士たちさえいちころになった。
≪040≫ 昭和文化は朝鮮や満州ともつながっている。大陸浪人や馬賊が行き交い、山東出兵は侵略の野望に満ちていた。こういうこと、戦後以降の日本ではもはやまったく想像するだにできないことだろう。しかし、一言で日本の二〇年代を一人の短い生涯によって象徴させるなら、ひょっとすると宮沢賢治をあげるべきかもしれない。賢治の『春と修羅』は大正末年の一九二四年の刊行だ。三七歳の生涯を終えたのは昭和八年、一九三三年のことだ。日本が満州事変に突入し、忌まわしい日々に揉まれていった矢先、賢治は透徹した表象に全身全霊を賭け、その言葉の錬丹術を鉱物的結晶のごとくに究めていた。本巻では与那覇恵子が賢治のページをうけもっているが、そこには賢治は日本を「異人の目」で見ていたという適確な指摘がしてある。
≪041≫ まあ、こんなふうに短い案内をしていっても詮方ないだろうが、総じてはともかくも一九二〇年代はかつてないポップとヒップとクールの奇瑞ともいうべき爛熟を集約させたのである。それがどうなったかといえば、一九二九年、ウォール街の大暴落とともに終焉を迎えた。
≪042≫ 恐慌から立ち直った米欧が見せたものは、金融政策とアーリア主義と流線形とアールデコと、そしてナチスの抬頭である。日本はひたすらアジア大陸と太平洋への野望に盲進していった。それらのことについては、このシリーズの別の巻に詳しい。
≪01≫ 昭和六(一九三一)年九月十八日、関東軍は奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖の南満州鉄道の鉄路を爆破した。関東軍は、この爆破は張学良の東北軍による破壊工作だと発表すると、ただちに軍事行動に移り、翌日までに奉天・長春・営口を占領した。特務機関長の土肥原賢二大佐が奉天の臨時市長となり、部下だった甘粕正彦はハルビン出兵の口実づくりのため、奉天市内各所に爆弾を投げこんだ。
≪02≫ 満州事変の発端である。暗黒の昭和史はもはや後戻りできなくなった。このシナリオを裏で書いたのは関東軍参謀の石原莞爾で、実行者は板垣征四郎だった。
≪03≫ 石原莞爾は山形県鶴岡の警察官の子で、陸軍幼年学校で軍人にあこがれて育ち、のちに外交官となった東政図にアジア主義を叩きこまれるとともに熱烈な日蓮主義者となった。田中智学の国柱会に接近するなかで、その日蓮主義は過激になっていく。
≪04≫ 田中智学は文久の日本橋の生まれで、十歳のときに日蓮宗門に出家して、しだいに当時の宗門の教義に疑問をもった。明治三四年に『宗門之維新』を書いて侵略的宗門という過激なコンセプトを提示して、一種の宗教的軍事主義と皇道ファシズムを説いた。日本は世界に先駆けて「法華経」を受容して、これを国際社会に広めるべきだというのである。日本国体学も説いて、高山樗牛や姉崎正治が支持した。大正十一年の『日本国体の研究』に「八紘一宇」を解説した。
≪05≫ まだ十代だった宮沢賢治は田中智学の国柱会に惹かれ、友人の保阪嘉内に息はずませながらこんな辞を書いている。「日蓮主義者。この語をあなたは好むまい。私も曾ては勿体なくも烈しく嫌ひました。但しそれは本当の日蓮主義者を見なかった為です。東京鴬谷国柱会館及『日蓮聖人の教義』『妙宗式目講義録』等は必ずあなたを感泣させるに相違ありません」。
≪06≫ その田中智学の三男に里見岸雄がいた。里見の『日蓮主義の新研究』はジャーナリズムにもてはやされ、石原莞爾はその里見をベルリン時代に迎えて深い仲になっていた。里見はのちに立命館大学法学部教授となり、「国体学科」を創設している。
≪07≫ 翌昭和七年一月、上海事変がおこる。一見、複雑な事件だが、上海に日本山妙法寺の末寺にあたる妙発寺があり、そこの僧侶たちが托鉢に出て共同租界からそれた馬玉山路あたりで、タオル工場・三友実業公司の従業員に襲われたことが導火線となった。
≪08≫ 実は仕組まれていた。三友実業が強力な抗日組織の拠点であったこと、この事件に激高した日本人青年同志会がタオル工場を襲ったこと、中国の官憲が出動して日本人を射殺したことなどは計算ずくだった。さらに海軍まで出動して事態が拡大していったのだが、それもヨミ筋に入っていた。日本人青年同志会による襲撃を指導したのは重藤千春という大尉で、日蓮主義者だった。
≪09≫ このシナリオは最初は板垣征四郎が書いて、上海の日本公使館武官補佐の田中隆吉が実行にあたった。粛親王(清朝王族)の第十四王女で川島浪速の養女となった「男装の麗人」川島芳子らが暗躍した。のちに、その田中を五・一五事件の青年将校の一人、山岸宏海軍中尉がアジトを襲って問責した。山岸も日蓮主義者だった。
≪010≫ 上海事変から一ヵ月後、血盟団事件がおこる。前大蔵大臣の井上準之助が襲われた。犯人は磯崎新吉の弟、小沼正とわかったが、背景は見えない。つづいて三月、団琢磨がピストルで撃たれた。犯人は菱沼五郎と名のった。
≪011≫ やがてこれらのテロの背後に「一人一殺」を宣誓する血盟団なる秘密組織があることが浮上した。首謀者は井上日召である。やはり激烈な日蓮主義者だった。
≪012≫ 日召は東洋協会専門学校を中退して明治四三(一九一〇)年に満州に渡り、満鉄の社員となりつつ参謀本部の諜報活動にかかわっていた。帰国後は国家革新運動をおこして大正十四(一九二五)年に護国聖社を結成した。血盟団は昭和七(一九三二)年に組織したばかりで、そこで小沼や菱沼らに「一人一殺」を叩きこんだ。日召はこれらのテロによって破壊が建設を生むと確信し、これを「順逆不二の法門」とよんだ。団員たちは「法華経」を唱えてテロに向かった。
≪013≫ 一方、このころ日夜に「法華経」二十八品を読誦していた北一輝は、そのたびにおとずれる霊夢を「神仏言集」に書きつけていた。松本健一はそれを“霊告日記”と名付けている。昭和四年から昭和十一年の二月二八日までつづく。二・二六事件の二日後、憲兵が北を逮捕する日までである。“霊告日記”の帳面には「南無妙法蓮華経」の大書が、左右には明治大帝と西郷南洲の肖像が掲げられていた。
≪014≫ その北のところへ参謀本部ロシア班にいた橋本欣五郎が訪れて、満州の蜂起に対応して国内でクーデターをおこすべき計画をうちあける。北はこれには賛成せず、弟子にあたる西田税を推した。西田には彼が書いたともくされる「順逆不二之法門」というパンフレットがある。
≪015≫ 北にうちあけられたクーデターは、橋本が独自に組織した桜会による三月事件、十月事件として知られている。この未遂に終わったクーデター計画は形を変えて二・二六事件になった。
≪016≫ このように昭和の血腥い決定的舞台からは、数々の日蓮主義者の動向が濃厚に見えてくる。このことは昭和史を学ぶ者にはよく知られていることなのだが、登場人物が宗門とのかかわりを深くもつために、たとえば「日蓮主義と昭和ファシズム」とか「法華経と北一輝と石原莞爾」といった視点を貫こうとする論文や書物はほとんど綴られてこなかった。本書はそのタブーを破ったものである。
≪017≫ 著者の寺内大吉が浄土宗の僧侶であって、かつ作家でもあることがこのタブーを破らせたのであろう。本書でもわずかにフィクショナルなキャラクターを二、三入れて“小説”の体裁をとっている。しかし調べがつくかぎりにおいて、ほぼ縦横無尽に日蓮主義者と軍事思想の関係動向を追いかけた。副題もずばり「二・二六事件への道と日蓮主義者」と銘打たれた。
≪018≫ 本書は昭和ファシズムがなぜ日蓮主義思想と結びつくかという謎をとくために、田中智学、里見岸雄、井上日召、北一輝、石原莞爾といった大物以外にも多くの人物を登場させているのだが、なかにはあまり知られていない人物が何人か出てくる。
≪019≫ 日蓮主義は右ばかりに流行したわけではなく、左にも共鳴者をふやしたのだが、その一人に妹尾義郎がいた。本多日生との関係がある。日生は井上円了やハルトマンの影響を受けた日蓮宗妙満寺派の改革者で、顕本法華宗や天晴会を組織した。
≪020≫ 妹尾義郎は広島で「桃太郎」などの銘酒をつくる酒屋の子に生まれた。そうとうに学業に秀でていたようだ。ただ体が悪く、一高に入るも胸の疾患で途中退学をし、故郷で回復をまって今度は上海の東亜同文書院を受験した。トップで合格した直後、また発熱してこれらの道をすべて断念している。かくて一転、仏教者として生きようと決意して千ヵ寺の廻国修行に旅立った。途中、出会ったのが岡山賀陽町の日蓮宗妙本寺の釈日研で、ここで日蓮の一種のボランティア精神ともいうべき活動の魂を受け継いだ。
≪021≫ そこへ田中智学の「国柱新聞」の過激な話題が入ってきて、にわかに国柱会への熱を募らせた。大阪の中平清次郎の紹介で智学を訪れるのだが、門前であしらわれる。この時期、国柱会の門を叩いた青年はそうとうに多かったが、「一人一殺」の秘密を要求するためか、門前払いも少なくなかったらしい。宮沢賢治もその一人、妹尾義郎もその一人である。
≪022≫ やむなく妹尾は統一閣の本多日生のもとを訪れ、ここで大日本日蓮主義青年団をおこして、機関誌「若人」を編集しはじめた。それが大正八年のことである。そのころの日生は統一的日蓮主義運動を推進しつつあった。
≪023≫ 大正も末期に近づくと、日本の状況はそうとうに混乱する。大胆な改革や革命を叫ぶ者も多く、一方で満川亀太郎、北一輝、大川周明らの「猶存社」や「行地社」、上杉慎吉の「国本社」などが右寄りの名乗りをあげ、他方で堺利彦や大杉栄の無政府主義、安部磯雄の社会民衆党、麻生久の日本労農党などが勃興しつつあった。しかし、多くの宗教者は左と右の政治蜂起に挟撃されるような立場にあったのである。
≪024≫ 改革の意志をもった妹尾もどちらに進むか迷っていた。結局、昭和二年に岡山で立正革新党を旗揚げして、まず政治の宗教化を謳い、ついで新興仏教青年同盟いわゆる「新興仏青」をおこした。
≪025≫ ここから先、妹尾の宗教思想はしだいに左傾化をするのだが、そのような妹尾に文句をつけたい日蓮主義者たちがいた。それが現代における不受不施派を標榜する「死なう団」である。西園寺公望、山室軍平、田中智学、そして妹尾義郎を抹殺リストにあげていた。
≪026≫ 妹尾義郎と「死なう団」。 この関係は、まさに明治大正のアジア主義と昭和の興亜主義との裏側をつなぐ奇怪な糸である。「死なう団」は昭和八年夏に集団で「死のう、死のう、死のう」と叫びながら行進していったところを逮捕されたので、ジャーナリズムからはこう呼ばれているが、正式名称は日蓮会殉教青年党で、その母体は江川桜堂が創始した宗教結社である。本多日生の影響下にあった。三三歳で病死した江川のあとを追うように殉死者が続いた。妹尾が暗殺リストに入っているのは、妹尾が日生のもとにいながらここから離れて日生批判の言動をふりまいているという理由からである。
≪027≫ 本書はその奇怪な糸をぞんぶんに手繰り寄せ、昭和の仏教にひそむ今日では考えもおよばない壮絶な苦悩を描きだしている。ここではこれ以上の紹介は遠慮しておくが、おそらくその苦悩を描けたことが本書の価値であろう。
≪028≫ ちなみに妹尾には全七巻におよぶ日記があって、家永三郎がこんなことを書いている。「日本の歴史上、前後に比類のない恐怖・暗黒の時期である昭和十年代を誠実に生きぬいた一知識人の、その時点に書きとめられたなまなましい記録の筆を通して、想像を絶する当時の内的・外的状況の諸様相を私たちに垣間見せる貴重な史料でもあるのであって、ひとり妹尾個人の精神生活の軌跡をたどるに役立つにとどまらない、高い価値をもつ文献である」。
≪029≫ それにしても日蓮をめぐる社会思想というものにはただならないものがある。昭和日蓮主義ともいうべき思想にかかわった本書に登場する人物たちの、その後の活動にも看過できないものがある。
≪030≫ たとえば里見岸雄は国体科学連盟を創立して美濃部達吉の天皇機関説を攻撃、さらに日本国体学会をおこして立命館大学に国体学科を創設した。戦後も憲法改正を主張して昭和三一年に「立正教団」を創設した。また、井上日召も血盟団事件で無期懲役となったのだが、その後に出獄して三木卓・四元義隆・菱沼五郎らと「ひもろぎ塾」を設立、戦後は農村地域をまわって講演活動をつづけ、昭和二九年には「護国団」を結成した。
≪031≫ おそらくはこれからも、現代の北一輝、平成の石原莞爾、二一世紀の妹尾義郎の輩出を妨ぐことは、きっと不可能であるとおもわれる。
≪032≫ ところで今夜の千夜千冊をアップロードしたあと、大谷栄一の『近代日本の日蓮主義運動』(法藏館)という大著が刊行されていることに気がついた。すぐに書店に走って取り寄せてもらった。一読、たいへんユニークで大いに考えさせられるものになっていた。田中智学と本多日生に発した「二つのN」をめぐって詳しいのである。「二つのN」とはNippon(日本)とNichiren(日蓮)のことをいう。直後に会った中村雄二郎さんにその話をしたら、「ああ、あれね。盲点をつかれたねえ」と感心していた。
≪033≫ [追記]その後も大谷栄一は『近代仏教という視座―戦争・アジア・社会主義』(ぺりかん社)、『日蓮主義とはなんだったのか』(講談社)など、一貫して日本の近代思想やアジア主義にひそむ日蓮主義のソート・ケミストリーを研究しつづけている。近代思想と日蓮主義の関係を知るためにも、今日の創価学会の活動の奥を知るためにも、もっと話題になるべきだ。もう一冊、佐藤哲朗の『大アジア思想活劇』(サンガ)という本も紹介しておく。副題が「仏教が結んだ、もうひとつの近代史」で、とくにダルマパーラを通してアジアと日本をつなぐ共創思想を追っている。
≪01≫ 三島は「愛国心は嫌いだ」と言った。 僕も恋闕を秘めつづけたい。
≪02≫ この本はきのう読み終わったばかりだ。前夜、アーノルド・ブラックマンの『東京裁判』についてアップロードしたあと、何かがすっきりしないので恵比寿の有隣堂に寄って何冊かの本を買ってきたのだが、近くの喫茶店で最初にこの本を開いて読み出したら、とまらなくなった。
≪03≫ たいへんおもしろかった。もともと鈴木邦男については、一水会の活動を始めたころから関心があった。『腹腹時計と〈狼〉』が刊行されたときは、その年のベスト10の収穫だと周囲に褒めまくったほどだったし、その後の横断的な言動にも注目するものが少なくなかった。ただし最近の活動や発言には疎く、新右翼の総帥はさてどうしているのかと思っていた。ちなみに「新右翼」という命名は猪野健治さんによる(152夜・第7巻)。
≪04≫ そういうこともあって、本書が新鮮に映ったのだろう。中盤ちょっと中だるみ、後半を皇位継承問題に絞ったせいか冴えが乏しくなるが、それでも一貫して狙いがぶれず、おおいに読ませた。こんなふうに始まっている。「僕」というのが鈴木邦男である。
≪05≫ 僕は日本一の愛国者だと断言できる。「君が代」は5000回以上歌い、「日の丸」も5000回以上揚げた。靖国神社には500回も参拝したし、自衛隊の基地祭でストリッパーを呼んだと聞いて防衛庁に抗議をして逮捕され、釧路に日ソ友好会館が建つと聞けば「許せん」と思って抗議に行って機動隊と乱闘になり逮捕された。
≪06≫ 左翼のデモのプラカードに天皇の似顔絵があればカーッとなって殴りこんで逆に袋叩きにあい、不敬な記事をのせた出版社を襲撃したこともある。東郷健が演出した舞台で天皇に扮した男がマッカーサーに扮した男に後ろからオカマを掘られている場面では、思わず舞台に駆け上がって大乱闘になった。愛国心がなければ、誰がそんな危ないことをやるもんか。僕はそうやって40年も右翼をしているのだ。
≪07≫ そのあいだ、僕は命を賭けてやってきたつもりだが、世の中はちっとも変わらなかった。変わりつつあるかなという小さな手応えもない。いつも「右翼のたわごと」と一蹴されてきた。
≪08≫ ところが最近、世の中が変わった。世相や国民の意識が奇妙に変わってきた。ソ連が崩壊し、東欧がなくなり、日本に左翼もいなくなった。そのとたん、である。にわか右翼、オタク右翼、新保守、ぷちナショナリストがどっとふえてきた。政府も文部科学省も日の丸・君が代を強制し、改憲も辞さないという雰囲気になってきた。日本一の愛国者と自負する僕でさえ戸惑うくらいだ。
≪09≫ いったい、どうしてこんなふうになったのか。鈴木は訝り、ニセの愛国心で日本が埋まっていくような危惧をおぼえる。そんなとき、ずっと課題のように読んできた『決定版三島由紀夫全集』全42巻の後半にさしかかって、こんなふうにあることにギョッとする。
≪010≫ 実は私は「愛国心」といふ言葉があまり好きではない。何となく「愛妻家」といふ言葉に似た、背中のゾッとするやうな感じをおぼえる。
≪011≫ この言葉には官製のにほひがする。また、言葉としての由緒ややさしさがない。どことなく押しつけがましい。反感を買ふのももつともだと思はれるものが、その底に揺曳してゐる。
≪012≫ 昭和43年(1968)1月8日に「朝日新聞」に書いた文章だった。その2年後に三島は市ケ谷の自衛隊で自決した。鈴木は三島こそは正真正銘の愛国者だと思ってきたのに、三島は愛国心という言葉は嫌いだと言う。どういうことなのか。
≪013≫ 鈴木は考えこんだ。三島は「もしわれわれが国家を超越してゐて、国といふものをあたかも愛玩物のやうに、狆(ちん)か、それともセーブル焼の花瓶のやうに愛するといふうのなら、筋が通る」と書いている。しかし、国家は犬でも花瓶でもないのだから、そのようには突き放せない。われわれは国家の一員であって、自分だけがそこから離れて高みに立ってこの国を愛するなどというのは、そうか、ひょっとして傲慢なのかもしれない。思い上がりかもしれない。鈴木はそのことに気がつかされて、ハッとする。それなのに自分は愛国心を安売りしていたのではないか。「量の愛国心」が気になってばかりいて、「質の愛国心」を陶冶してこなかったのではないか。
≪014≫ 三島の文章をきっかけに、鈴木はこのようなことを考えていく。そして、さらにその奥に分け入っていく。そうすると鈴木を打擲した三島の指摘がもうひとつあったのである。それは、日本人の情緒的表現の最高のものはあくまで「恋」であって、決して「愛」などではないと断言していることだ。
≪015≫ 三島は愛国心は国境による擬装であって、それゆえアメリカ人もフランス人も日本人も同じような愛国心があるとするのは欺瞞だと断じたのである。なるほど、もしもアメリカ人と日本人が同じような普遍的な愛国心をもっているというのなら、日米戦争などおこらなかったはずなのだ。愛国心は「愛」とはいいながら、自国しか愛さない。自国愛だけに酔っている。
≪016≫ まして、三島がいう通りなのだとすると、日本は「恋」なのである(ぼくもそう思う)。相手がどう思っているかなどどうであれ、一途に思いを寄せていく。それが恋である。恋心だ。鈴木は、そうだ、日本には「恋闕」(れんけつ)という言葉があったじゃないかと思い出す。ぼくも第942夜の北一輝の夜に書いたことだ(全集「千夜千冊」第5巻所収)。
≪017≫ だいたいこんなふうに始まっていくのだが、ここから先がさらにおもしろい。
≪018≫ 鈴木邦男はぼくの1歳上の早稲田大学出身者である。福島県に生まれて二高に落ち、大学をめざすためミッションスクールに入った。キリスト教にはどうしてもなじめなかった。ふりかえってみれば、そのときすでに「愛」は苦手だったのだ。
≪019≫ 早稲田に入ったとき、「生長の家」に入った。大本教から分かれた谷口雅春が昭和5年前後に始めた新興宗教である(第1147夜『鎮魂行法論』参照)。谷口も早稲田中退で、『生命の実相』全40巻によって“活字による布教”の先駆者となった。インテリ宗教とも呼ばれた。その信仰の基本は「万教帰一」であるが、熱烈な天皇崇拝者でもあった。鈴木は肺病に苦しんだ母親が「生長の家」によって救われて入信して以来、子供のころから子供会に連れられていて、そういう谷口に好ましい印象をもっていた。
≪020≫ 実は、ぼくの母も伯母も「生長の家」にかかわっていて、すでに何度か書いたことだが、『甘露の法雨』というポケットに入るような教典を持たされていた。ただし、ぼくは教団活動にはまったくかかわらなかった。
≪021≫ 鈴木はその「生長の家」の赤坂乃木坂にある学生道場に入った。道場では毎朝、国旗掲揚台の前で36人が整列し、君が代を歌った。寮生活をしながら、たいていの行事にも参加した。谷口はそのころ、宗教家は個人の危機を救うものだが、いまは日本が危篤状態なのだから、この病いを治さなければならないと説いていた。とくに共産主義に日本が犯されることに対して身を挺してでも闘うべきだと説いていた。
≪022≫ それがすべての始まりだったようだ。鈴木は自治会の委員長を2期つとめ、街頭に出て、左翼と闘うことになったのだ。
≪023≫ さて、三島の指摘によって愛国心の本性を考えるようになった鈴木は、「恋闕」という言葉から、もうひとつのことを思い出す。森田必勝のことである。
≪024≫ 森田は三島とともに市ケ谷で自決した「楯の会」の精鋭だった。魂だった。鈴木は早稲田の学生のころ、2年後輩の森田を民族派の活動に引きこんでいた。つまり右翼活動に引き入れた。そのころの森田はいつも明るくニコニコしていたが、仲間が「俺はいつでも国のために死ねる」とか「おまえにその覚悟があるのか」といった論争を始めても、まったく加わらなかった。硬派だった。鈴木が恋人はいないのかと聞くと、「俺の恋人、誰かと思う。神のつくりし日本国」と言って笑うだけだったらしい。この言葉は徳富蘇峰(885夜・第5巻)の言葉である。
≪025≫ やがて鈴木のまわりの活動家は次々に戦線を離れ、就職したり結婚したりしていった。それが1970年11月、森田必勝は三島とともに市ケ谷で自決した。鈴木は「うしろめたさ」と「負い目」を感じ、それが一水会を結成するきっかけになった。ふりかえってみれば、鈴木の愛国心は三島と森田に振り回されてきたのである。
≪026≫ こういうことを、鈴木は本書に屈託なく書き綴っていく。いったい愛国心って何なのか。清水幾太郎の岩波新書『愛国心』、赤尾敏の大日本愛国党、サミュエル・ジョンソンの「愛国心はならず者の最後の避難場所である」、愛国と憂国とのちがい、重信房子のお父さんが「娘は愛国者です」と言っていたこと(重信の父親は井上日召の血盟団に参加していた)…。これらを覗きながら、愛国心の来し方行く末を見る。
≪027≫ 日本の右翼の源流は玄洋社に始まっている。玄洋社については第896夜に頭山満の著作をとりあげたのでここでは省略するが、一言でいえば「皇室を戴いて民権運動をやる」という行動思想にもとづいていた。憲則では、「第1条「皇室を敬戴すべし」、第2条「本国を愛重すべし」、第3条「人民の権利を固守すべし」となっている。
≪028≫ 鈴木の原点もさかのぼれば、ここにある。したがって玄洋社がどのような活動をしていたかを知ることが、おおざっぱにはその後の右翼の羅針盤になる。「皇室を戴いて」と「民権運動をやる」が一緒になっているのがキーポイントだ。この二つに、ともに愛国心が絡まっている。
≪029≫ 日本の民権運動は明治10年代に勃興した自由民権運動をもって嚆矢とする。このとき「愛国公党」とか「愛国社」といった結社が次々に生まれていった。この「愛国」はパトリオティズムの訳語にあたる。日本のばあい、そこには愛郷心も含まれていた。いや、土佐や会津をはじめ初期の自由民権は愛郷心をこそかきたてた。それがしだいに民権愛国となり、国会開設運動になっていく。
≪030≫ 玄洋社も民権から国権に転向したと批判された時期がある。日清戦争後の三国干渉などを体験するなか、列強の言いなりにならざるをえない日本の国情がやるせなく、玄洋社は国家の宿命を左右するにはアジアの革新と連動することが必要だと思うようになり、天佑侠を組織し、朝鮮の東学党を支援し、孫文やビハリ・ボースを援助した。一方で大隈重信の暗殺を企てたりもした。
≪031≫ たしかに民権は国権と混じっていったのである。もっと正確にいえば大日本帝国という国家が自由民権のすべてを吸収した。愛国心や愛郷心は、ただそれを唱えるだけではすべて国家の装置のひとつになるようになっていったのだ。大アジア主義も日本の国家の方針に吸い上げられていった。
≪032≫ それなら玄洋社も同じじゃないかと、ふつうの近代史はそこを批判する。橘孝三郎の愛郷塾も非難する。
≪033≫ しかし鈴木は、そこにひとつの決定的なちがいを確認する。玄洋社は「天皇制の輸出を考えていない」ということだ。なるほど、この言い方はうまかった。日本は満州進出を機に朝鮮半島の経営に乗り出し、朝鮮神宮をつくり、創氏改名をおこない、日韓併合にもちこんだ。これは天皇制の輸出だった。この方針はすでに秀吉にもあった。第1038夜に書いたように、秀吉は北京に後陽成天皇を移そうと考えていた。大唐関白には秀次をさしむけようとした。そういうことは玄洋社は考えない。ということは、日本の右翼は天皇制によってはアジアを(また世界を)見ないということなのである。
≪034≫ これは日本の右翼や新右翼の特色をよくあらわしている。鈴木はこのような“掴み”がまことにうまい。
≪035≫ では、日本人の愛国心は天皇制に結びつく必要があるのか。鈴木はそんなことはないと言う。たとえば日本共産党は愛国心の最も強い政党かもしれないが、天皇制についてはゆくゆくなくなってもいいと考えている。そういう立場はいくらあってもいい。愛国はそういうものだ。
≪036≫ しかし鈴木にとっては、天皇制を積極的に肯定する理由がある。日本の天皇制はフランス革命の「自由・平等・博愛」に相当するものであるからだ。 このことを説明するのに、本書では鈴木は坂口安吾の『堕落論』を持ち出している。坂口は次のように書いていた(873夜・第5巻)。
≪037≫ 私は天皇制についても、きわめて日本的な(したがってあるいは独創的な)政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生み出されたものではない。天皇は時にみずから陰謀をおこしたこともあるけれども、概して何もしておらず、その陰謀は常に成功のためしがなく、島流しとなったり、山奥に逃げたり、そして結局つねに政治的理由によってその存立を認められてきた。
≪038≫ 国を亡ぼすのは「無智」と「愚かさ」とである。日本を尊崇するのは結構だが、「悪しく敬はば国亡ぶべし」である。予は断然叫ぶ。社会主義を日本国体化せよと。 坂口はそう書いて、天皇や天皇家は権力ではないし、政治的実験でもないのではないかと問うた。だから日本にとっては天皇は「権威」にしかすぎず、それなら「孔子家でも釈迦家でもレーニン家でもよかったはず」なのだが、「ただ代わりうるものはなかった」のだと書いた。
≪039≫ 鈴木も大筋そのような判断をする。他のシンボルでもよかった。が、日本においては天皇しかなく、また天皇こそがふさわしいのだと。
≪040≫ もしそうだとすると、そこまではとりあえずそうだということにすると、さあ、ここで奇妙な天皇争奪戦がおこってしまうのである。幕末維新はそれが「玉」の奪い合いになったが、明治後期以降や昭和史ではそれが「天皇の御心」の争奪戦になった。ここから右翼思想が研ぎ澄まされ、過剰になり、腐敗もし、激越にもなった。
≪041≫ つまり「天皇=愛国=自己正当化」がそれぞれの行動思想をめぐって争奪されたのだ。昭和史とはその歴史であった。血盟団は経済主義者に一人一殺を向け、青年将校は「君側の奸」を取り除くために2・26事件をおこし、統制派の軍部は天皇主義を大東亜共栄圏に駆使した。
≪042≫ そのように見ていくと、三島や森田が天皇万歳を叫んで自決していったのは、そうした天皇争奪の情けないほどの忌まわしさに終止符を打ちたかったのかとも見えてくる。
≪043≫ 三島は自決の前に『文化防衛論』を書いた。そこで「文化」と言ったのは「天皇」そのものだった。『英霊の声』では「などてすめろぎは人となりたまひし」と書いた。三島には2・26のときの天皇は神ではなく人にすぎなかったのである。
≪044≫ ところで、このような推論を展開しつつ、鈴木が次のようなことを書いているのが興味深かった。
≪045≫ 1988年、鈴木は竹中労を一水会の機関誌「レコンキスタ」に取材した(竹中労については第388夜参照)。そのとき話題が三島の『文化防衛論』になったらしいのだが、竹中がすかさず「あれのネタ本は里見岸雄ですよ」と言ったというのだ。
≪046≫ 里見は過激な法華経主義者の田中智学の三男である(第378夜『仮城の昭和史』参照・全集「千夜千冊」第5巻所収)。智学は明治後半に「国柱会」をおこし、宮沢賢治や井上日召や石原莞爾を引きつけた。昭和日蓮主義とテロリズムの源流になっている。その三男の里見は『天皇とプロレタリア』『国体に対する疑惑』『国体法の研究』『天皇の科学的研究』『日本国の憲法』などを著し(200冊ほど著書がある)、機関誌「国体文化」を発行した。昭和16年には立命館大学の法学部教授となって、翌年には国体学科を創設、戦後は『日本国体学』全13巻を刊行した。竹中労はその里見のロジックに三島の文化防衛のモデルがあると言ったのだ。
≪047≫ 鈴木はもともと北一輝・大川周明と並んで里見岸雄を偉大な右翼思想家と感じてきた男だ。それでも、その里見に三島のモデルがあるとは気がつかなかった。さっそく読んでみると『天皇とプロレタリア』には次のように書いてある。
≪048≫ これが北一輝の『日本改造案大綱』や『国体論及び純正社会主義』と通じるものであることは、すでに橋川文三や松本健一まで、さまざまに指摘されてきた。しかし、三島の文化防衛論すなわち三島の最後が里見と結びついているという指摘は、意外なものだった。
≪049≫ 本書には、随所にこのような意外なエピソードや指摘が組みこまれている。そこがおもしろかったのだが、それだけでなく、そこに鈴木邦男の卓見がキラリと光り、そのあたり、最近の『国家の品格』などというていたらくが多い愛国論議のなかで、なかなかの出色なのである。感心した。たとえば竹中労についても、「竹中こそが里見岸雄だったのではないか」という、まことに切れ味のよい抜き身を光らせていた。
≪050≫ まあ、本書についての案内はこのくらいにしておく。熱暑の夜陰に、前夜の『東京裁判』での未消化感を払拭するのに、とても気分のいい読書感想となった。こういう本はありがたい。もっといろいろなことが書いてあったが、それは本書にジカに当たられることを勧める。
≪051≫ いや、肝心のことを書くのを忘れた。愛国者は信用できるのかというタイトルは、とうてい信用できない愛国者が溢れつつあって、日本はまことに困った国になりつつあるという意味なのだ。言わずもがなだろうが、念のため。